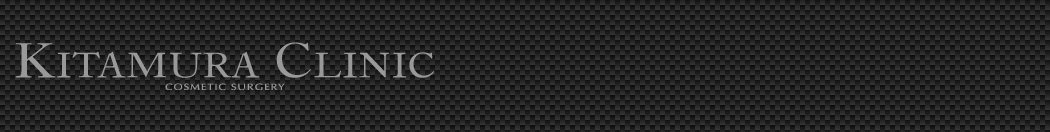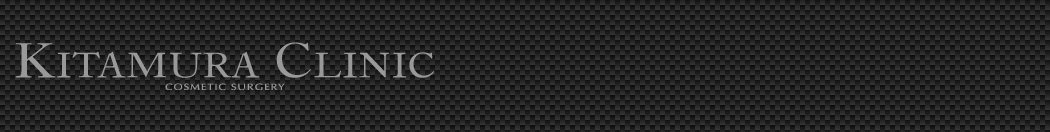映画やドラマの中で、時計はいつも印象的な役割を担ってきた。歴史ある駅舎のコンコースに据え付けられた大時計。あるいは、古い邸宅の大広間で静かに時を刻む柱時計。それらはさまざまな場面で効果的に登場し、「引き返せない現実」や「終わることのない流れ」というイメージを、見る者に想起させる。それは時計というものに対して私たちが漠然と抱いている、ある種特別な印象のなせるわざなのだろう。
時は決して立ち止まることも、後戻りすることもない。世界中の誰に対しても平等に、冷徹なまでに刻々と過ぎていく。その流れに抗うことは、誰にもできない。
腕時計は、そんな時の重みを一気に凝縮したものだ。手のひらにも納まってしまう小さなケースの中で、休みなく時は動き続ける。手首に巻いた時計の秒針の、そのひと刻みずつをじっくりと眺めるとき、何か厳粛なものを感じる人は決して少なくないはずだ。それは「自然の法則を垣間見る」という意識がさせることかもしれない。
|

|
その、時の重みを刻み続ける腕時計。現在では大小無数のメーカーが林立し、際だつ個性を放つブランドも数多い。そんな中にあって、「カルティエ」は名実ともにトップブランドの一角に君臨し続けてきた。
その始まりは19世紀の半ば、パリに開いたジュエリーブティックにさかのぼる。その後、親から子へ、さらに孫へと代替わりを続けていく中で、カルティエならではのデザイン様式を確立し、ついには英国王室御用達となる。時の英国王から「宝石商の王」という讃辞を受け、その後はポルトガルやロシアなど、各国の王室にもその素晴らしい作品の数々を納めるまでになっていく。
他のブランドと同様、カルティエもまた、ブランドとして成長し名声を高めるとともに、そのブランドイメージを使ってさまざまな分野の製品を手がけるようになっていった。ことに日本においては、バブル景気に湧いた1990年代に多くの製品が巷にあふれていった。バッグをはじめとする革製品、ペンなどのステーショナリー、ひところはタバコまであったが、これはすでに国内販売終了となってしまっている。
|